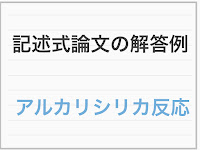合格者の解答例!アルカリシリカ反応の記述式論文
合格者の解答例!記述式論文の模範解答
コンクリート診断士試験に合格した際に、事前に準備していた解答例をポイントを抑えて解説します。
記述式論文の問題に出るテーマは何が出るかはわかりません。
どのようなテーマが出ても解答できるよう、主要なテーマの解答例は確実に準備しておきましょう!
また、コンクリート診断士の過去問を解く際の参考にもした頂ければ幸いです。
①変状からの推察
- 1980年代以前に建造。
- 躯体に亀甲状のひび割れが生じている。
- 鉄筋方向と並行して生じているひび割れが生じている。
- 1980年代以前はアルカリ反応骨材の規制がないこと。また、写真より、躯体に亀甲状のひび割れのほか、鉄筋方向と並行して生じているひび割れが生じていることから、アルカリシリカ反応によるコンクリートの膨張と推察する。
[補足・解説]
- 1980年代までアルカリ反応骨材の規制なし→1980年代以前はアルカリ反応骨材を使用した可能性あり
- アルカリ反応骨材は水分の供給により膨張するため、問題文の中に“漏水”の記載もあれば、漏水によりアルカリシリカゲルが膨張したと推察できる旨も記載する。
②詳細な調査
- 調査としてコアの採取を行い、アルカリシリカ反応の特徴を有するか確認する。
- 反応生成物の確認のために、走査電子顕微鏡またはEPMA等を使用する。
- 膨張量の測定のために、促進膨張試験の実施する。
- また、鋼材の健全性の確認のために、鋼材の腐食の程度を確認する。
[補足・解説]アルカリシリカ反応の特徴
- アルカリシリカ反応による変状→水の供給や空気と触れている可能性ある→鋼材腐食の恐れある
- コアの断面の骨材周辺に反応リムやゲル、ひび割れが生じることが多い。
- 走査電子顕微鏡やEPMA等を使用して確認する。
[補足・解説]骨材の判定
- 骨材にアルカリシリカ反応性試験法を行う。
- アルカリ濃度の減少量と溶解シリカ量を測定し、アルカリ反応骨材か否かを判断する。
③今後の劣化進行の予測
- 促進膨張試験により、残存膨張量を測定する。
④対策
- 残存膨張量が多い場合、アルカリシリカ反応を防ぐために、水分供給の阻止が必要になる。そのため、ひび割れ補修を行う。
- 強度不足、耐力不足の場合、外側に鉄筋を配置し、増厚コンクリートの施工を行う。また、せん断補強を目的に、炭素繊維を設置する。
さいごに
記述問題の解答時のポイントを紹介しました。
記述問題にアレルギーがある方もいるかもしれませんが、しっかり準備しておけば怖くありません。
短い試験時間で解答を書くには、劣化の種類ごとに記載する内容を事前に決めておくことが試験にパスするポイントになります!
そのためには、過去の問題集や解答例を参考に、試験前から準備することが大切です。
ちなみに試験問題集は、以下の観点で購入することをお薦めします。
- 試験の傾向を把握するためにも最新版であること。
- 5年分くらいの過去問と解答がある。
- さらには各問題の解説も記載があること。
上記の要件を満たす問題集のうち、こちらの問題集が非常に使いやすかったです。
※ アフィリエイト広告を利用しています。
コンクリート診断士試験の書籍は受験者数が限られるのか、入荷待ちやメーカー取り寄せになりやすいです。
必要な勉強グッズは早めに準備しましょう!
コンクリート診断士試験の問題集で他に何があるか気になる方は、こちらも参考にしてください。
解答文を作るのは時間がかかると思われそうですが、結果的に近道になりますので、しっかり準備しましょう!
あと、せっかく受験料払うのですから、最新の情報から傾向を把握して勉強した方が良いと思います。
また、資格関係の書籍は在庫がないと取り寄せになるので時間かかります。早めに準備を始めることで時間のロスを減らせます。
少しでもお力になれれば嬉しいです。応援してます!
最後に、劣化パターン別の解答文を準備した時のノートも紹介しますね!お役に立てば幸いです。
本ページ以外にも、勉強内容やテーマ別の試験のポイントも記載してます。
コンクリート診断士の試験勉強の方法やポイントはこちらに記載しました。
また、試験対策の重点を占める記述式問題の解答例も劣化パターン別に記載してます。
こちらのサイトマップで一覧にしていますので、勉強に活用ください。